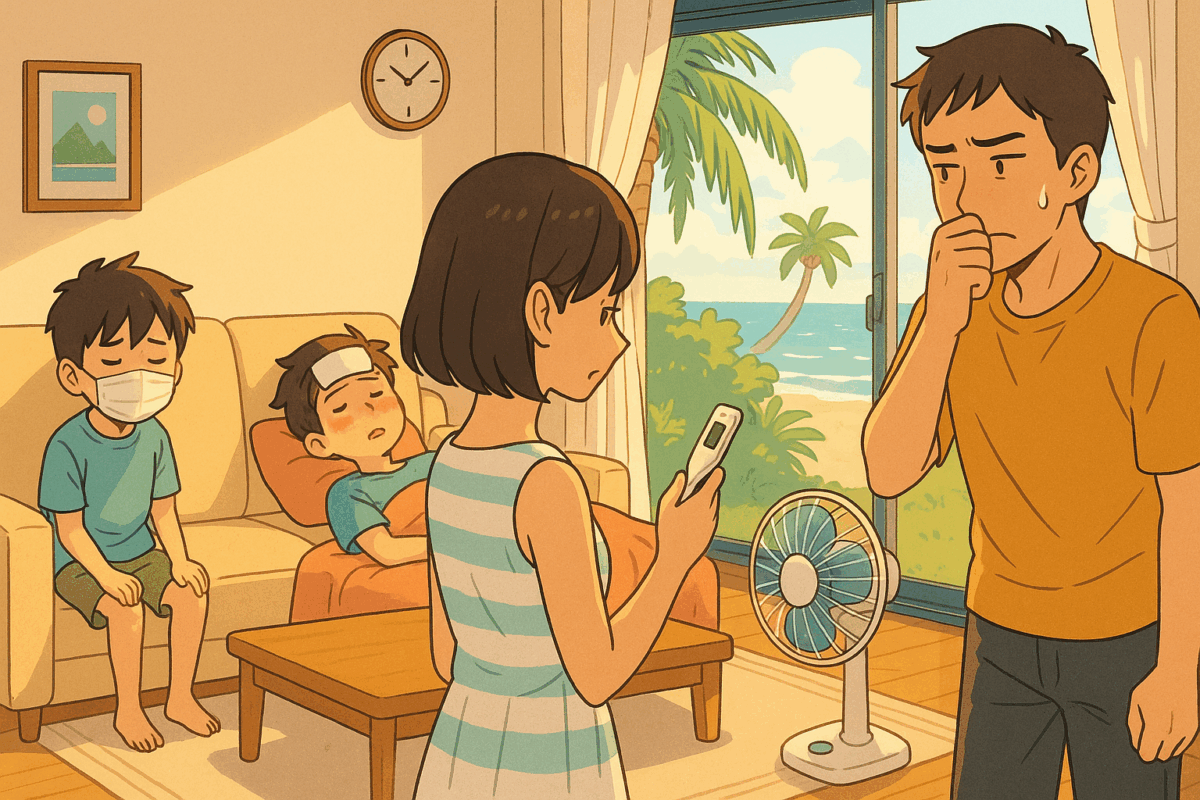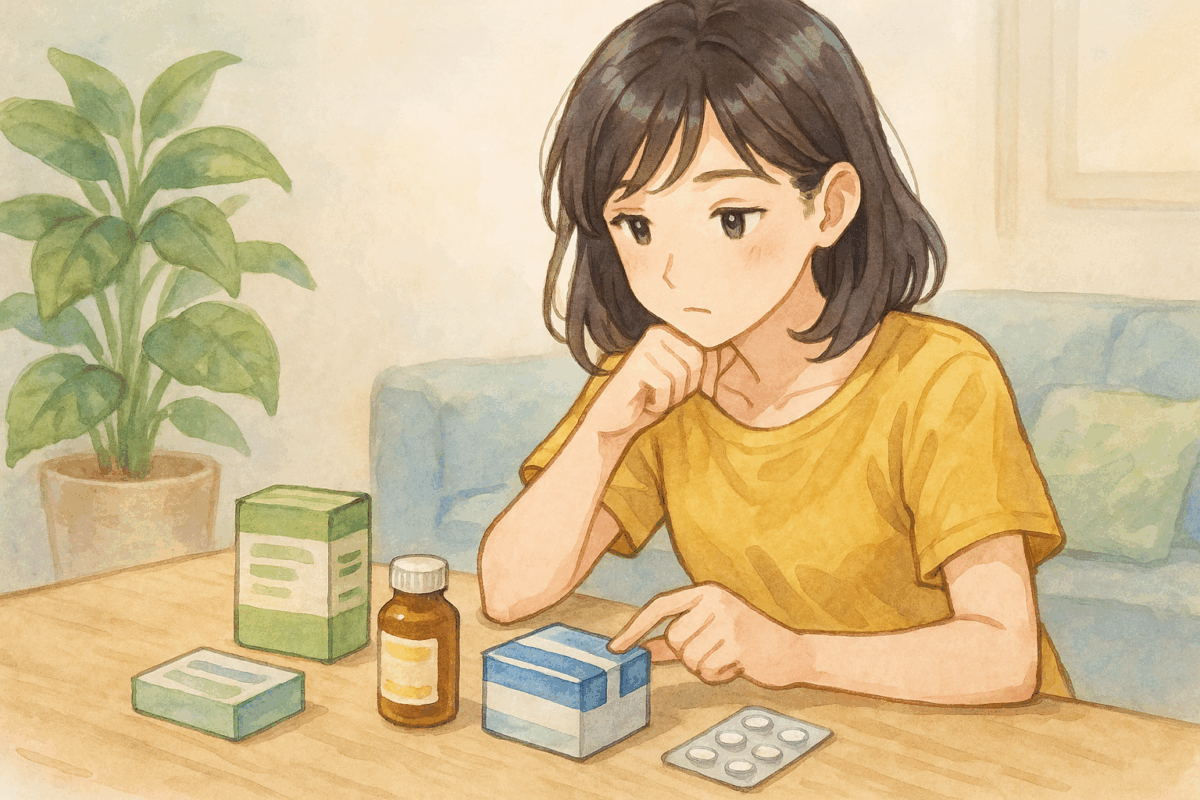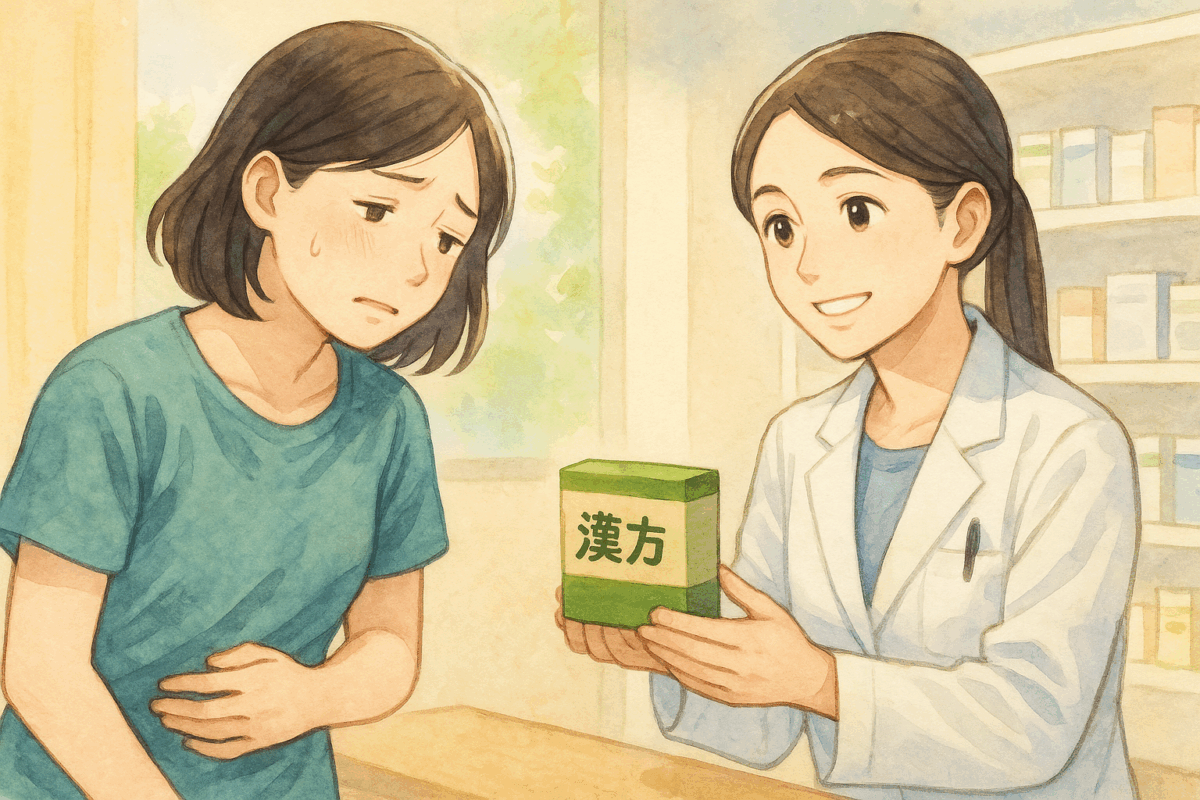
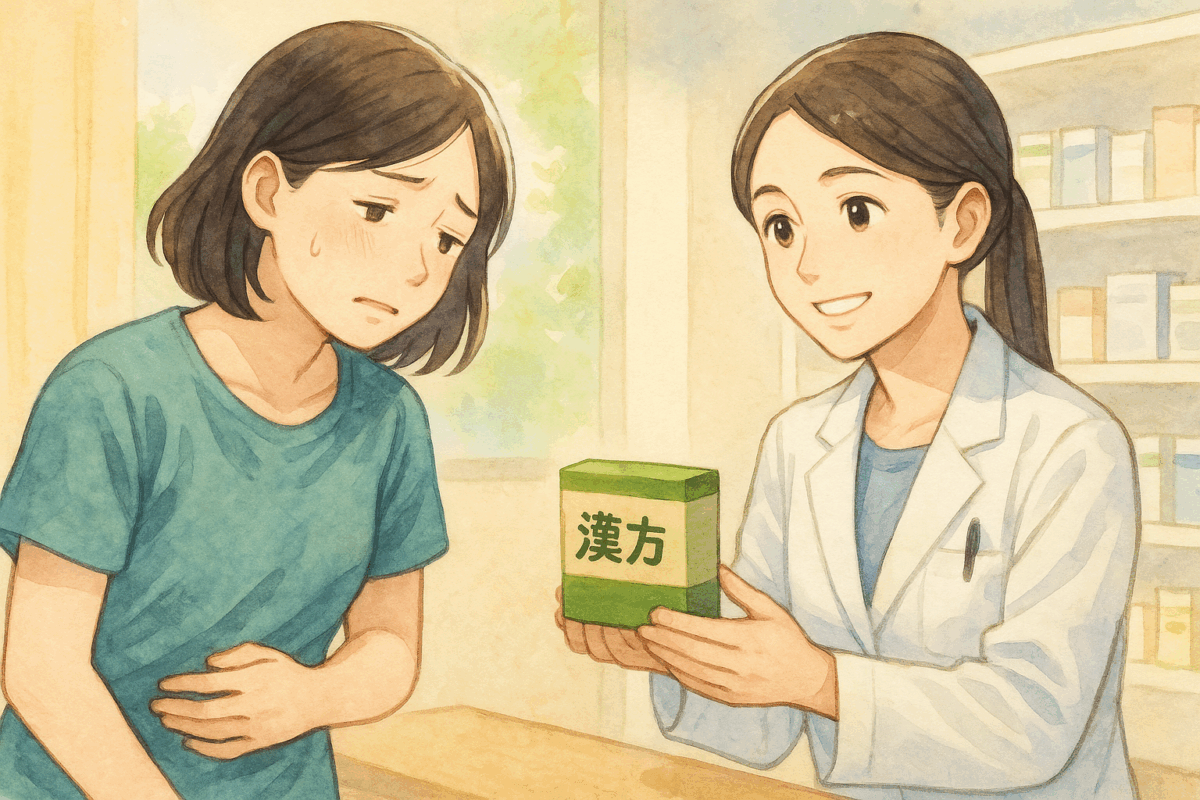
夏の胃腸バテに効く!薬剤師おすすめの漢方4選【補中益気湯・六君子湯ほか】
「食欲がない」「胃がムカムカする」…その症状、夏の胃腸バテかもしれません。
そんなとき頼りになるのが、体質に寄り添う漢方薬。
補中益気湯・五苓散・六君子湯など、薬剤師の視点で選び方とポイントを解説します。
夏バテ対策に、自分に合う漢方を見つけましょう。
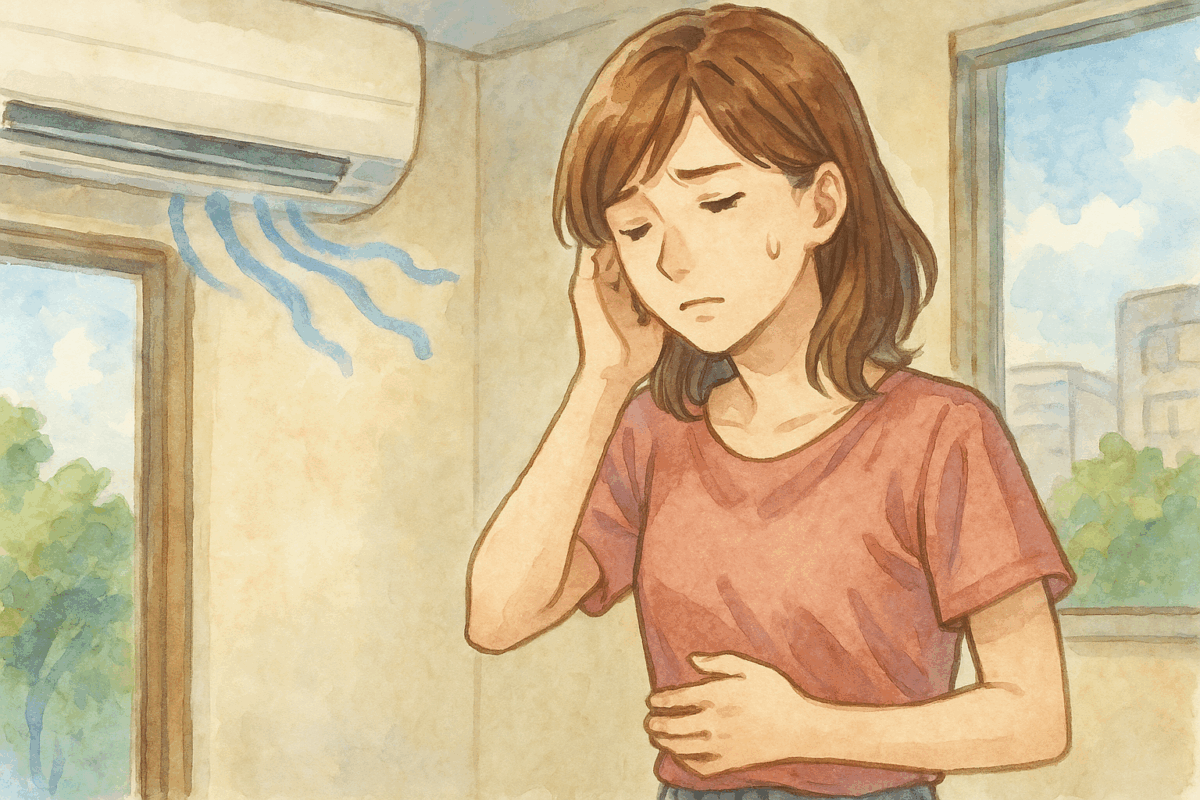
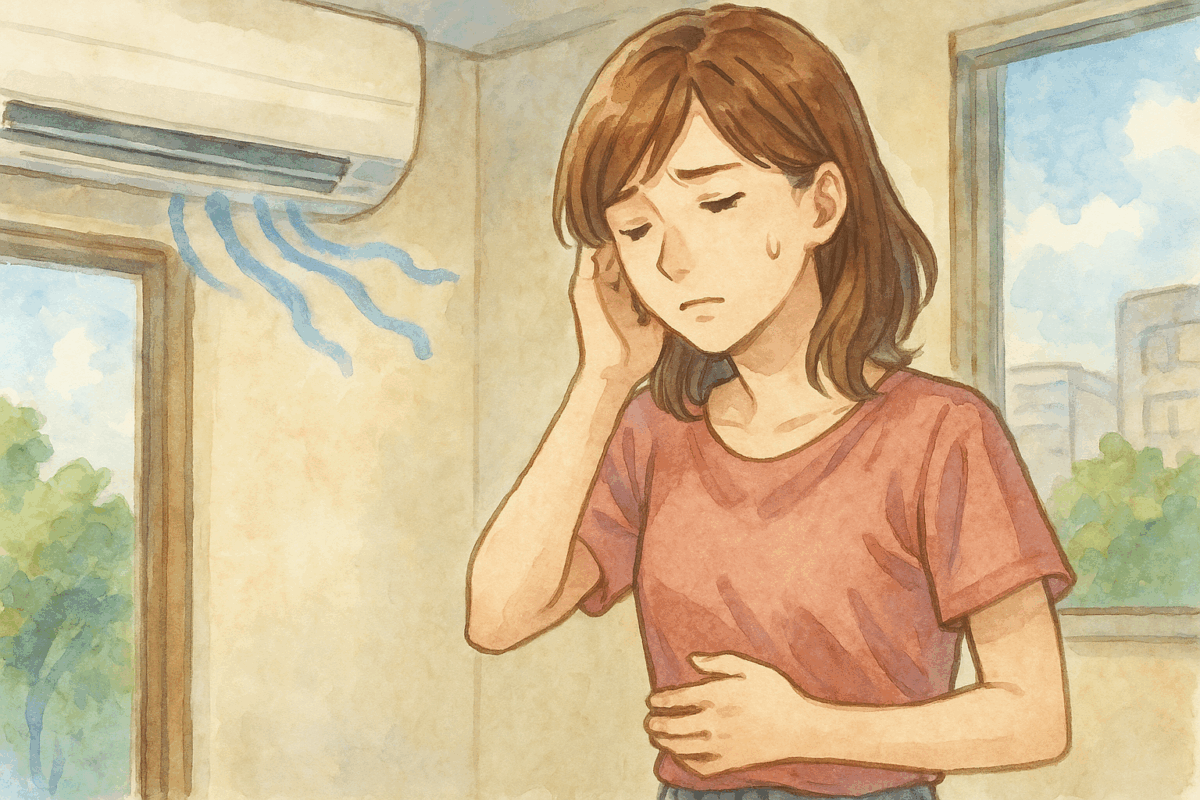
第1章:なぜ夏は胃腸が弱る?湿気と冷えが引き起こす不調
■ 夏バテ症状の代表は「胃腸の不調」
夏になると「食欲が出ない」「胃が重たい」「お腹を壊しやすい」といった声をよく耳にします。
これ、いわゆる“夏バテ”の症状ですが、実はその中心にあるのが胃腸の不調です。
胃もたれ、下痢、便秘、ムカムカ感など、消化器系の不調は夏に特に目立ちます。
暑さのせいで食欲が落ちるというだけでなく、実際に消化機能が落ちているケースが多いのが特徴です。
「夏は冷たい物ばかり食べてるからかな?」と片づけがちですが、実際にはもっと根本的な原因があるんです。
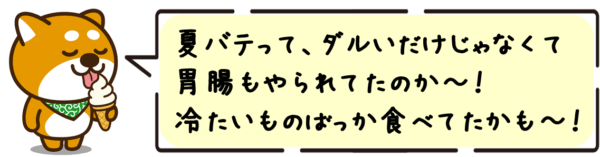
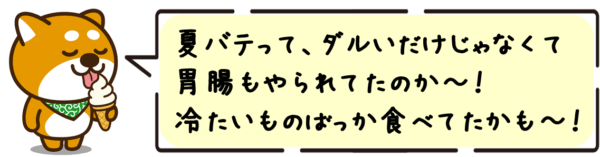
■ 漢方の視点:「脾(ひ)」は湿を嫌う
漢方では、消化吸収を担う臓器のことを「脾(ひ)」と呼びます。
この脾が、夏の“湿気”によって真っ先にダメージを受けると考えられています。
「脾は湿を嫌う」というのが漢方の基本。
つまり、高温多湿な日本の夏は、脾にとって最悪の環境だということです。
湿度が高いと、体の中に“余分な水分(湿邪)”がたまりやすくなります。
この湿邪は、胃腸の働きをにぶらせ、消化機能やエネルギー代謝を落としてしまうのです。
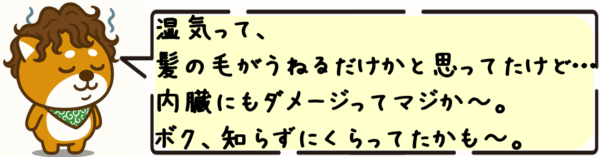
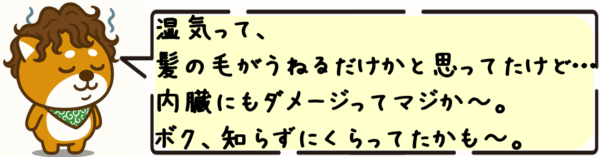
疲れやすい・だるい・気力がわかない、といった症状も「脾の不調」からくると漢方では捉えます。
夏バテは、まさにこの“脾のダウン”が引き起こす総合的な不調だと言えるでしょう。
■ 冷房・冷たい飲食・自律神経の乱れとの関係
夏の胃腸バテは、外気の湿気だけが原因ではありません。
現代の生活習慣もまた、胃腸に追い打ちをかけています。
たとえば、冷房の効いた室内で長時間過ごすこと。
エアコンによる“冷え”は、知らず知らずのうちに内臓の血流を低下させてしまうのです。
また、冷たい飲み物やアイス・冷たい麺などの摂りすぎも大きな問題。
胃腸が冷えて動きが鈍ることで、消化不良や下痢を引き起こしやすくなります。
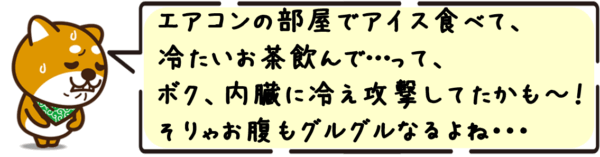
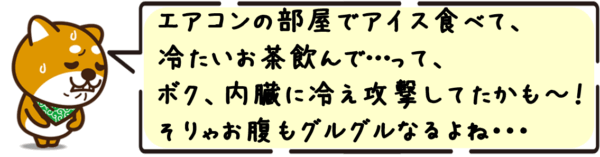
さらに忘れてはいけないのが、自律神経の乱れ。
寝苦しさや気温差によるストレスで、交感神経と副交感神経のバランスが崩れると、胃腸の働きにブレーキがかかります。
「夜になると胃がムカムカする」「朝からなんとなく調子が悪い」といった不調は、自律神経の乱れが背景にあるケースも多いです。
■ 舌苔(ぜったい)にあらわれる“隠れ胃腸バテ”のサイン
「まだ本格的な症状は出てないし、大丈夫」と思っている方も、実はすでに胃腸がSOSを出しているかもしれません。
漢方では「舌診(ぜっしん)」という診断法があり、舌の状態から体内の不調を読み取るとされています。
なかでも注目するのが、舌の表面にうっすらと見える“白っぽい膜”のようなもの。
これを舌苔(ぜったい)と呼びます。
この舌苔の「色」や「厚さ」は、胃腸の働きや体のバランスを反映しており、次のような変化があれば“隠れ胃腸バテ”の可能性があります。
✔ 苔がいつもより厚くなっている
✔ 苔の色が黄色っぽく濃く見える
✔ 舌全体がべたっとして見える
こうしたサインは、胃腸の機能が低下していたり、体に余分な熱や湿気がたまっている状態を示します。
暑さで汗をかき、冷たいものを多くとってしまう夏は、内臓がオーバーヒートしやすくなります。
そんなとき、舌はとても正直に反応してくれます。
朝の歯みがき前、鏡の前で舌をちょっと観察するだけでも、胃腸バテの予兆に気づくヒントになりますよ。
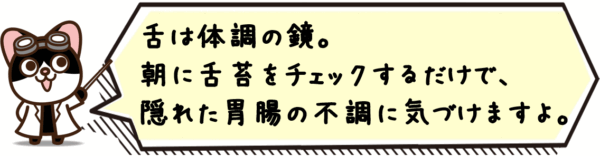
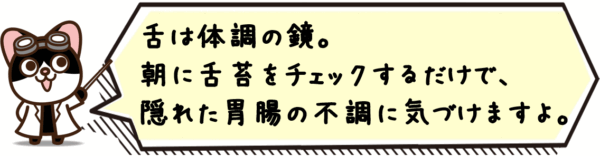
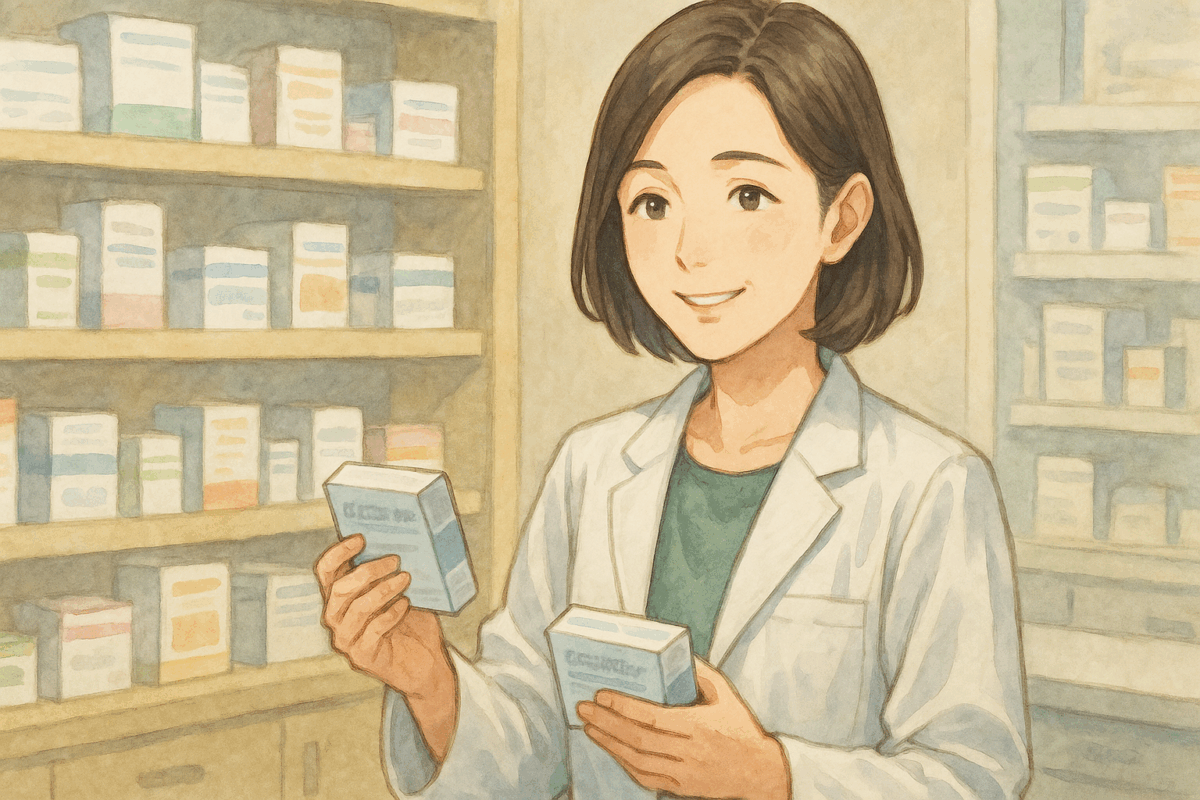
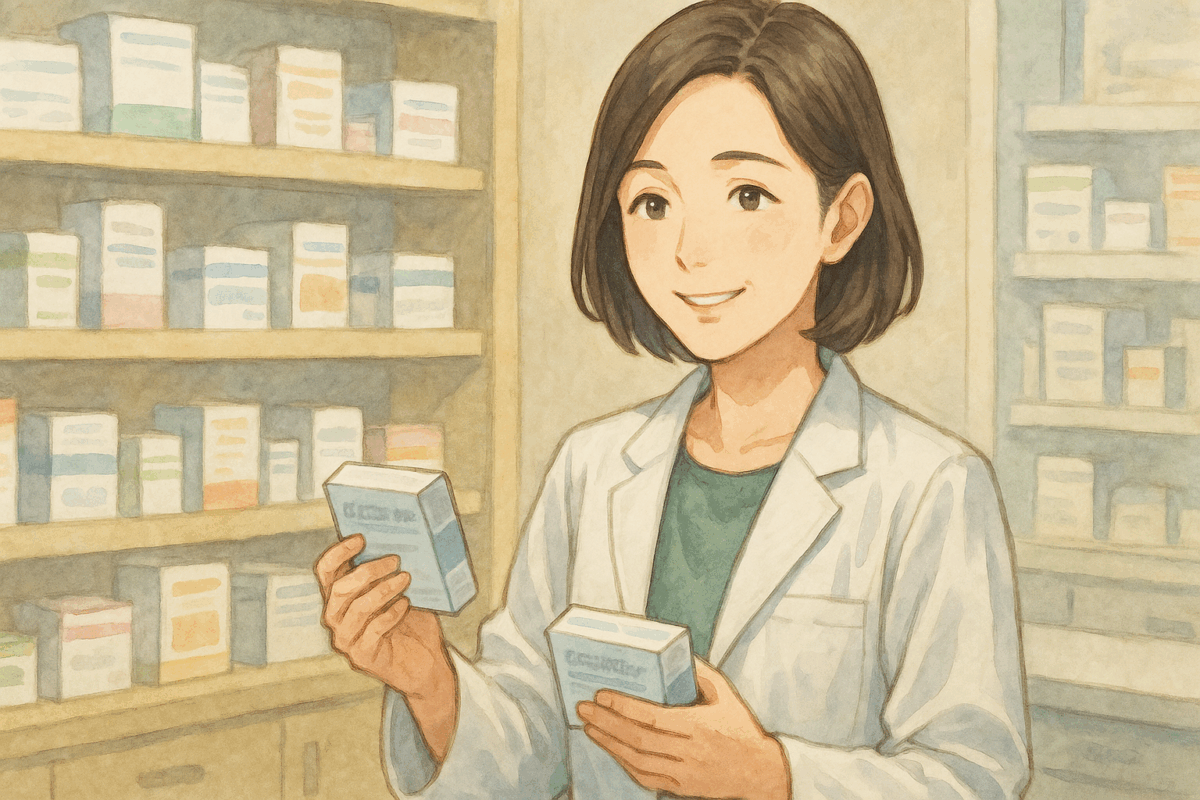
第2章:薬剤師がすすめる胃腸虚弱向け漢方薬4選
■ 胃腸虚弱と漢方の相性とは
夏になると「なんとなく胃の調子が悪い」「疲れが取れない」という声が急増します。
特に、食欲不振や下痢、胃もたれといった“胃腸虚弱”に関しては、西洋薬ではカバーしきれない慢性的な不調が目立ちます。
そうした不定愁訴に対応できるのが漢方薬です。
漢方は、体のバランスを整えることで根本的な改善を目指す考え方。
だからこそ、「冷え」「湿気」「疲れ」が重なる日本の夏には、体質に寄り添う漢方が力を発揮しやすいんです。
ここからは、薬剤師としておすすめしたい夏の胃腸虚弱に向いた漢方薬4種を紹介します。
■ 代表的な4処方の解説と適応症
【1】補中益気湯(ほちゅうえっきとう)|疲れやすくて食が細い方に
夏のだるさや無気力感、そして胃腸の機能低下が気になる人におすすめなのが「補中益気湯」。
名前の通り、「中(胃腸)を補い、気(エネルギー)を益す」処方で、消化機能が落ちて疲れやすくなっている体を立て直すのに向いています。
特に食欲がなくて横になりがち…という人は、早めに取り入れてもいい処方です。
【2】六君子湯(りっくんしとう)|胃が重たい・ムカムカする方に
「食べたいのに食べられない」「胃がつかえて苦しい」と感じたら、「六君子湯」がおすすめ。
消化器系を元気にする四君子湯に、理気作用のある半夏(はんげ)や陳皮(ちんぴ)などを加えた構成で、“胃の動きが鈍い”タイプの胃腸虚弱に合う漢方です。
実際、機能性ディスペプシア(FD)の改善にも使われていて、エビデンスもある処方のひとつ。
ムカムカ、食後の膨満感、吐き気が出やすい人に向いています。
【3】人参養栄湯(にんじんようえいとう)|冷え・疲労・貧血ぎみな方に
冷えや倦怠感、貧血傾向があって、食も細くなっている——そんな方にぴったりなのが「人参養栄湯」。
この処方は、“気(エネルギー)”と“血(けつ)”を同時に補う”という位置づけ。
冷え性で疲れやすい、体力が落ちてきた40〜50代女性に使われることも多いです。
夏場、エアコンで体が冷えきっているのに汗はかいて、というアンバランスな状態を整えるのにも有効。
胃腸が原因の冷えがある人にも合う処方です。
【4】五苓散(ごれいさん)|下痢・むくみ・頭重感がある方に
水っぽい下痢が続いたり、体がむくんで重い…そんなときには「五苓散」が定番です。
この処方は体の余分な水分(湿)を抜いてくれるのが特徴。
湿度が高い日本の夏にピッタリで、胃腸に湿がたまって働きが悪くなっているときに使われます。
「エアコンで冷えたあとにお腹がゴロゴロ…」という方にもおすすめです。
二日酔いや頭痛対策としても知られていますが、胃腸バテによる“水分トラブル”にも使える点は要チェックです。
■ 市販薬での入手可否と注意点
紹介した4つの処方は、すべて市販薬として購入可能です。
ツムラやクラシエ、コタローなどの大手メーカーが製造しており、ドラッグストアや通販サイト(AmazonやYahoo!ショッピングなど)でも取り扱いがあります。
ただし、以下の点には注意が必要です。
・各製品は「第2類医薬品」や「第3類医薬品」に分類されており、副作用のリスクもゼロではない
・漢方薬は体質との相性が重要で、自己判断で長期間使い続けるのは避ける
・発熱や激しい痛み、急性の症状には向いていないケースがある
・服薬中の薬がある場合は薬剤師または医師に必ず相談する
症状が長引く、悪化するようなら、専門の医療機関での診断を受けることをおすすめします。
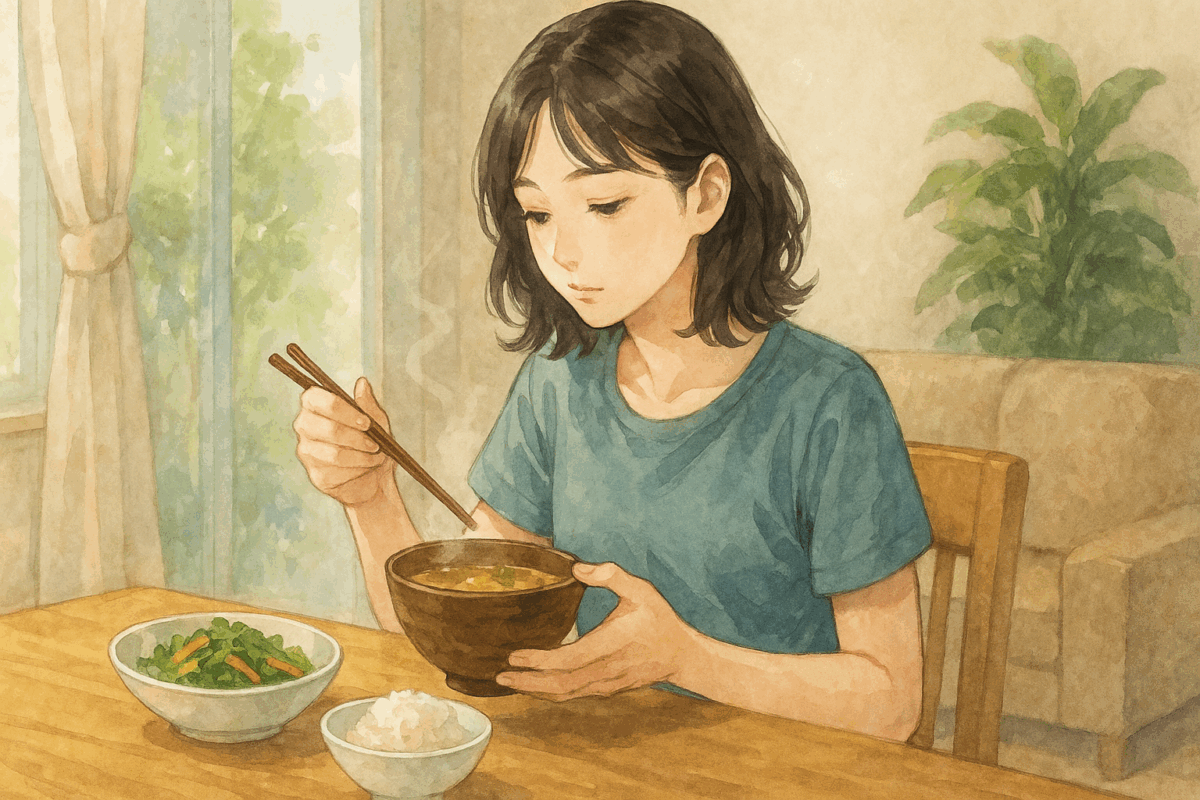
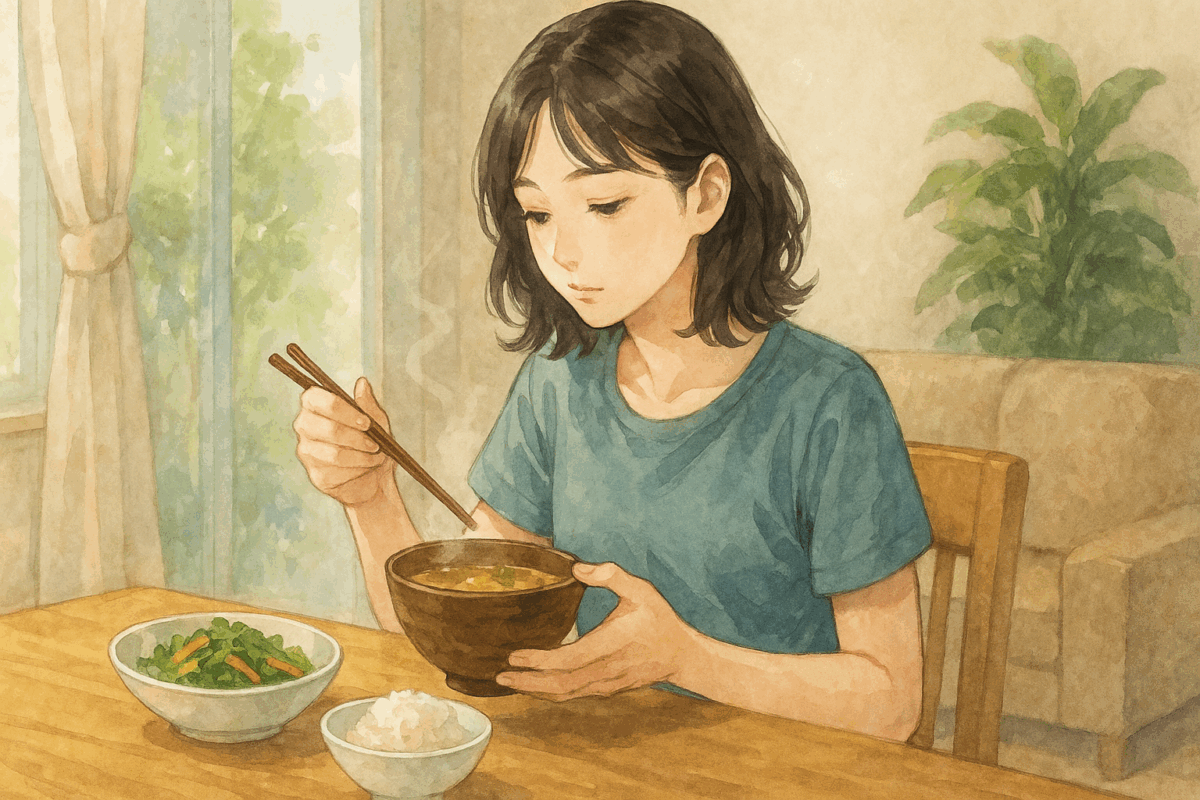
第3章:今日からできる!胃腸バテ予防の生活習慣
■ 温かい食事を1日1回は取り入れる
冷たいそうめん、アイス、ジュース…。夏はどうしても冷たいものに手が伸びますよね。
でも、胃腸は“冷え”が大の苦手。
内臓が冷えると、消化に必要な血流が低下し、胃の働きそのものが弱くなってしまいます。
できれば1日1回は、温かい味噌汁や煮物、スープなどを食事に取り入れてみてください。
「温かいものを食べる」だけで、内臓はじんわり元気を取り戻してくれます。
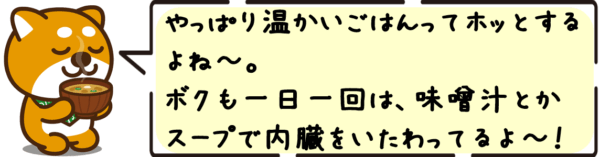
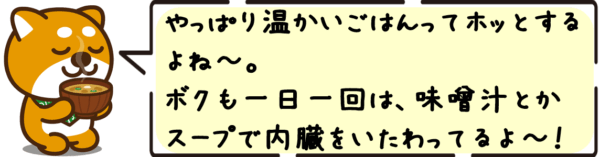
■ 食べる量は「腹七分目」が理想
胃腸バテを防ぐには、“食べすぎ”もNGです。
「夏バテだから、しっかり食べなきゃ!」と意気込んで重たいものを詰め込むのは逆効果。
漢方では、「脾(ひ)は満を嫌う」といわれます。
つまり、胃腸は「満腹状態」が苦手なんです。
理想は腹七分目。
「ちょっと足りないかな」くらいで止めておくと、消化もスムーズに進みやすくなります。
特に夕食は少なめにして、寝る前までに胃を空っぽに近づけておくことがポイントです。
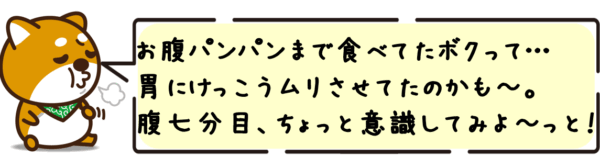
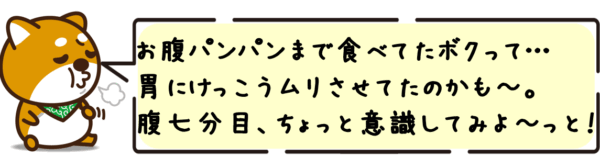
■ 冷たい飲み物は常温・白湯に置き換えを
夏の定番といえば、キンキンに冷えた麦茶やアイスコーヒー。
確かに気持ちいいですが、胃腸は急な冷たさで一気に動きが鈍くなります。
朝起きてすぐや、空腹時の冷たい飲み物は、胃にとって大きなストレス。
できるだけ常温の水や白湯に置き換えるのがおすすめです。
特に白湯は、内臓の冷えを防ぐだけでなく、水分の吸収効率もよく、脱水対策としても優秀。
一気に切り替えるのが難しい方は、「冷たい飲み物のあとに白湯をひと口」というスタイルでもOKです。
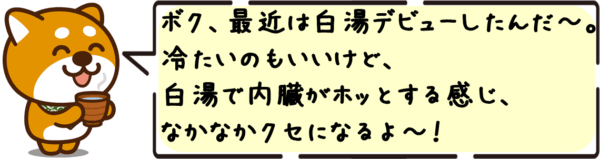
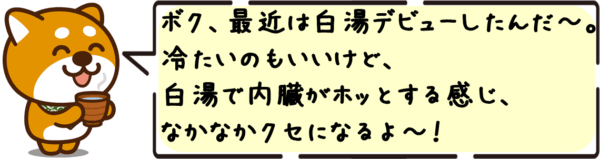
■ 入浴・睡眠・起床リズムを整える
胃腸がきちんと働くには、「夜の過ごし方」がかなり重要です。
特に意識したいのが、入浴と睡眠のタイミング。
冷房の効いた部屋に長くいると、内臓は芯まで冷え切ってしまいます。
そんなときは、ぬるめのお風呂(38〜40℃)に10〜15分浸かるのが効果的。
胃腸の血流を促し、リラックスすることで副交感神経が優位になり、自然と内臓も整います。
また、睡眠中に胃腸は“メンテナンスモード”に入ります。
夕食は就寝3時間前までに済ませるのが理想。
夜ふかしや寝不足が続くと、胃腸の回復力が追いつかなくなるため、起床・就寝のリズムも意識してみてください。
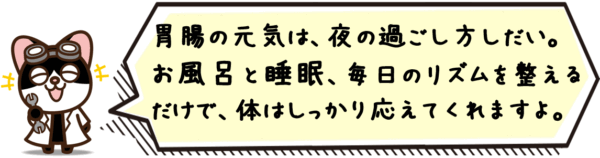
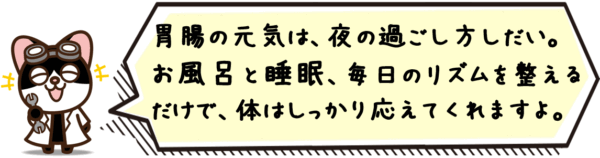
漢方薬も心強い味方ですが、日々の生活の積み重ねこそが胃腸を元気にします。
少しの工夫で夏の不調はぐっと軽くなりますので、できることから始めてみてくださいね。
まとめ|夏の胃腸バテ対策のポイント
・胃腸の不調は夏バテの根本原因:だるさや食欲低下も“内臓の疲れ”から起きている
・湿気・冷えが胃腸を弱らせる:特に日本の夏は漢方的にも過酷な環境
・漢方薬は体質と症状で選ぶ:六君子湯・補中益気湯など、市販でも入手可能
・生活習慣の見直しが効果大:白湯・温かい食事・腹七分目・舌苔チェックがカギ
・舌は胃腸の鏡になる:毎朝チェックで“隠れ胃腸バテ”を早期キャッチ
夏の胃腸バテは、薬だけではなかなか立て直しづらいんです。
漢方や生活の工夫を“組み合わせて”取り入れるのが、一番の近道です。
冷たいものばかりに頼る前に、白湯をひと口。
食べすぎる前に、「もう満足かな」と一呼吸。
そういった“小さな選択”が、夏をラクに乗り切る秘訣です。
無理なくできることから、始めてみてくださいね。
【参考情報】
この記事の作成にあたり、以下の公式情報を参考にしています。
ご自身での確認や商品選びの際にご活用ください。
◆ メーカー公式製品情報
クラシエ漢方|クラシエ漢方製品情報
ツムラ|一般用漢方製品一覧