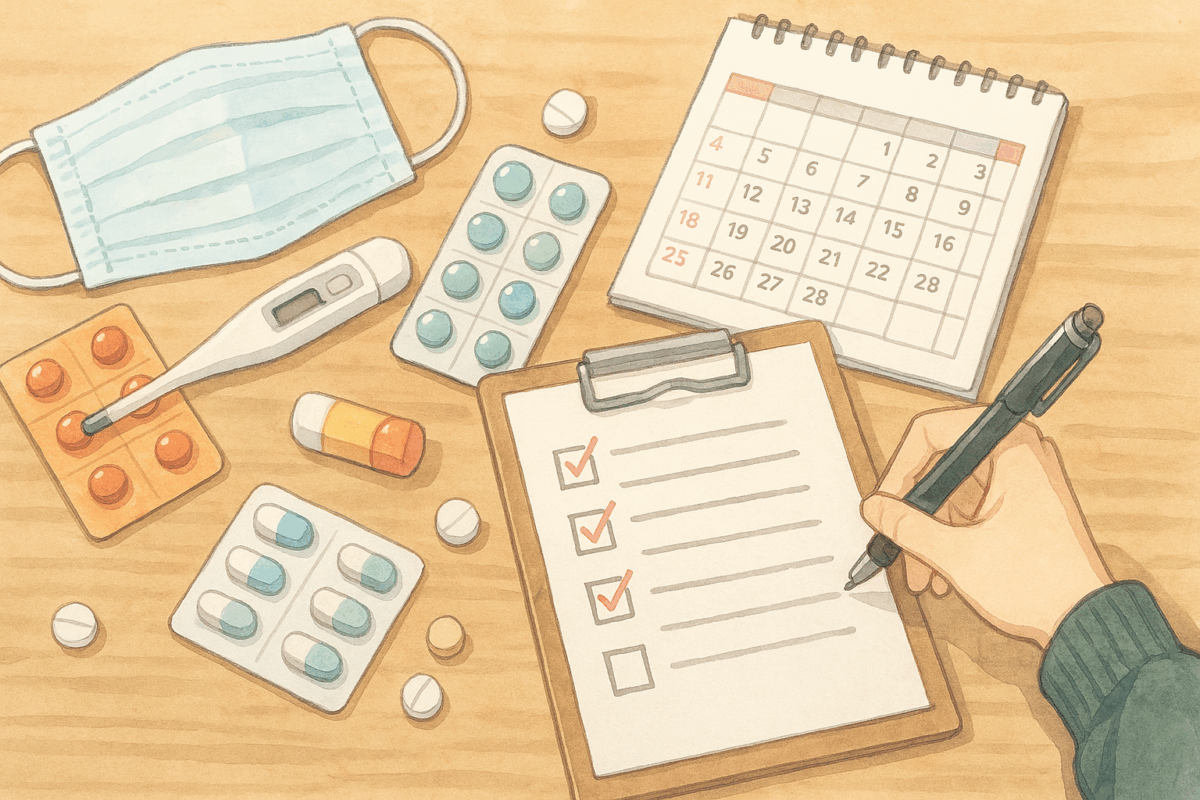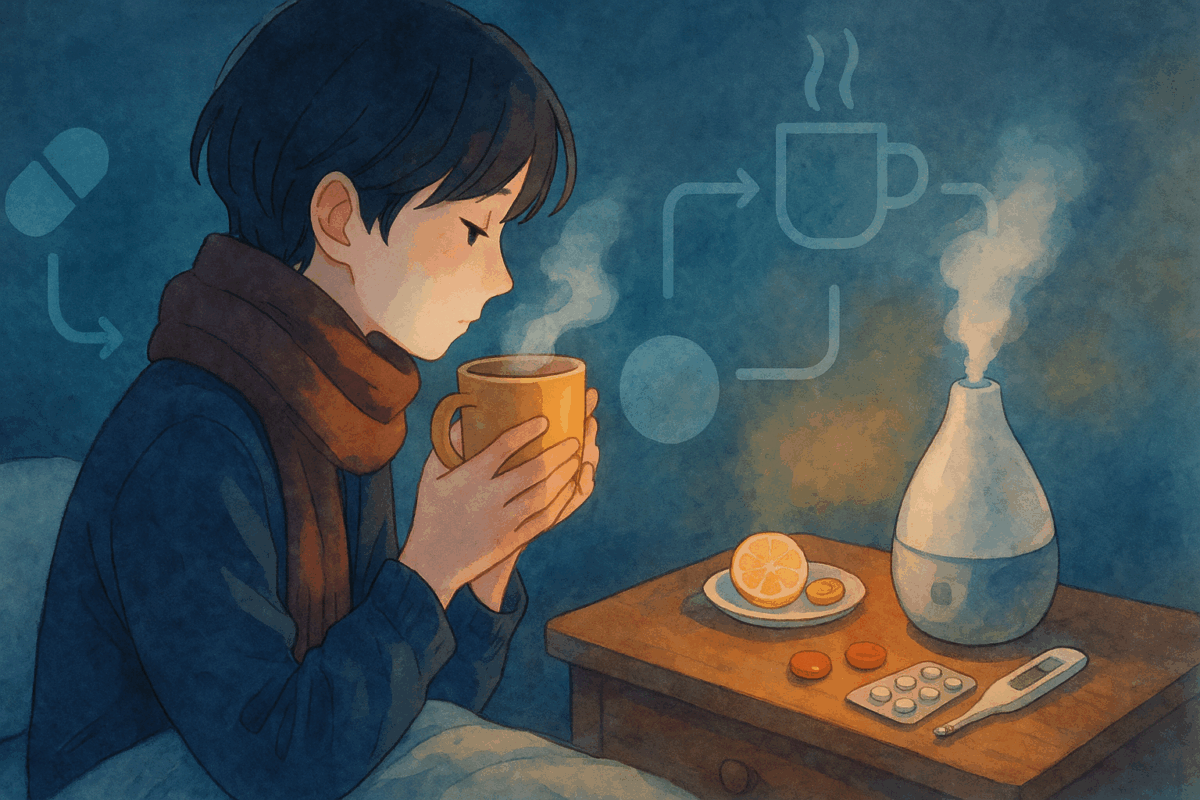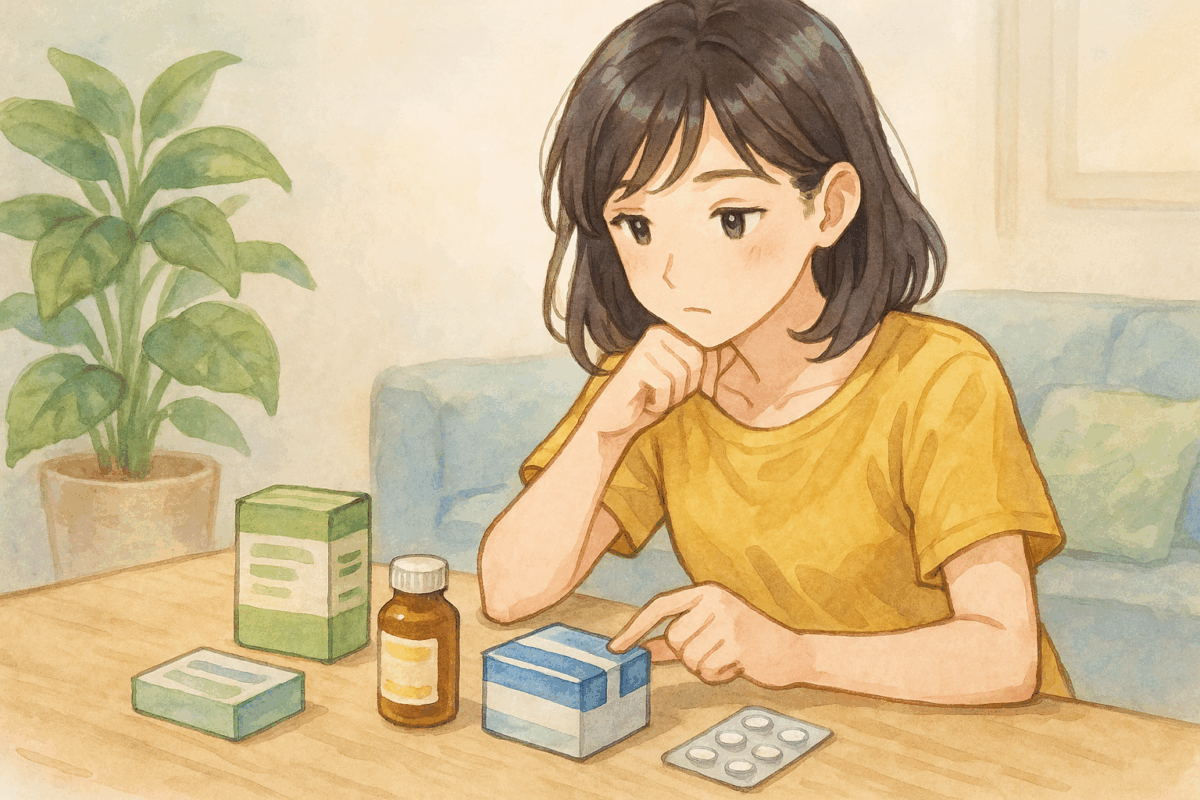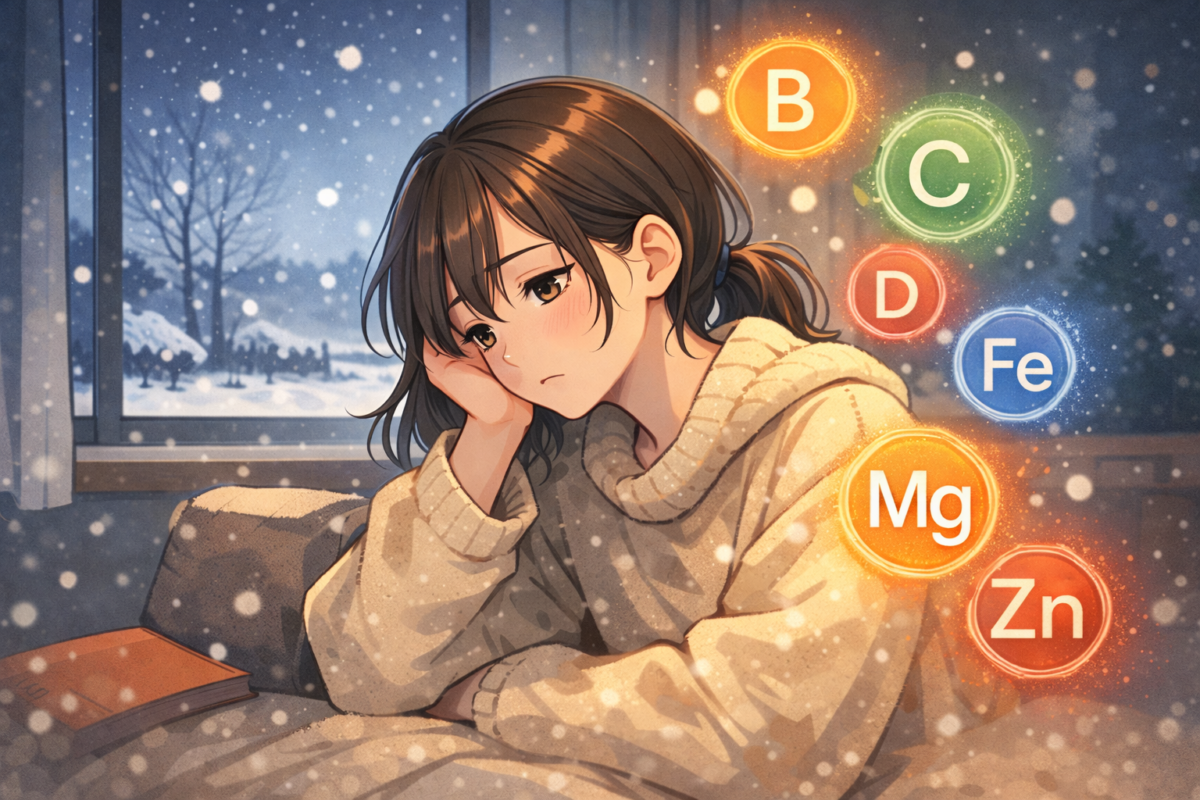市販で購入できる坐薬について、薬剤師が解説!
「市販でも病院で貰っているのと同じ坐薬は購入できる?」
「飲み薬ではなく坐薬を使うメリットってなに?」
このような疑問を抱えていませんか?坐薬はほかの薬と比べて種類が限られていますが、シーンによってはとても活躍してくれる薬です。
市販で購入できるものもありますので、いざというときに頼ってみるのもよいでしょう。今回は市販で購入できる坐薬の種類や、坐薬を使うメリットなどについて紹介します。
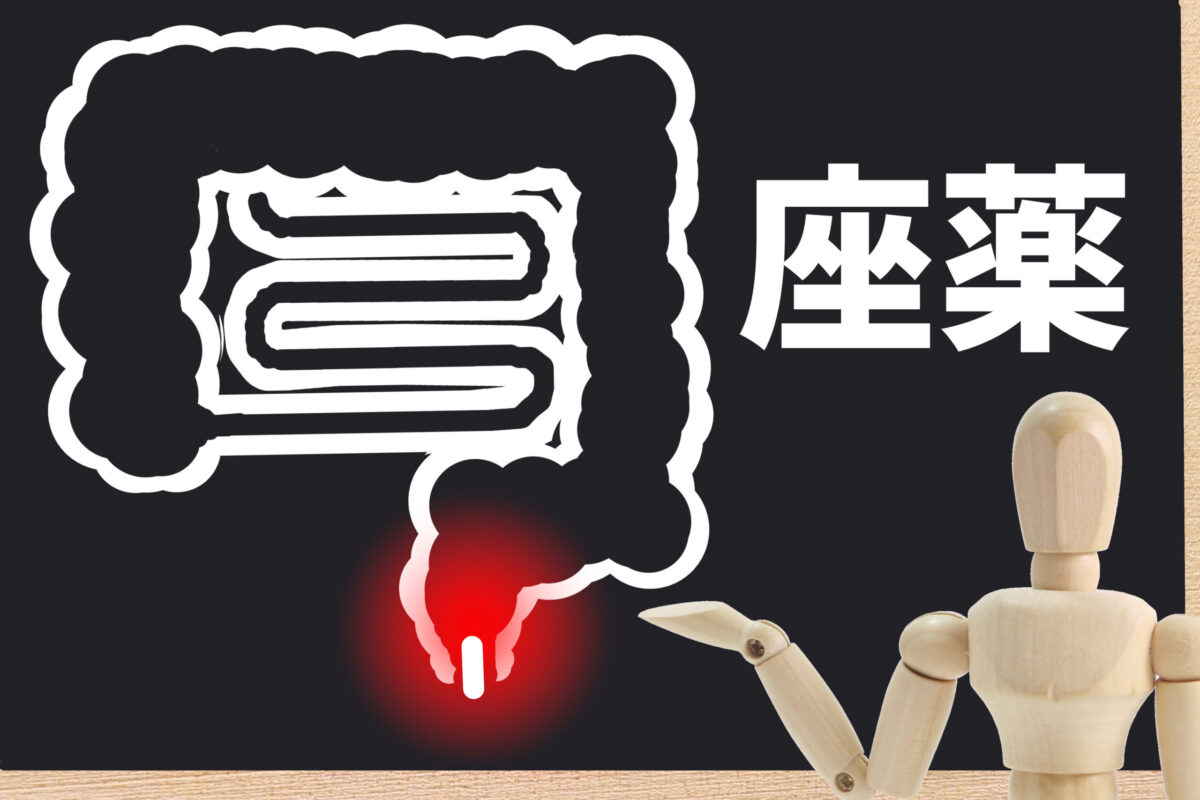
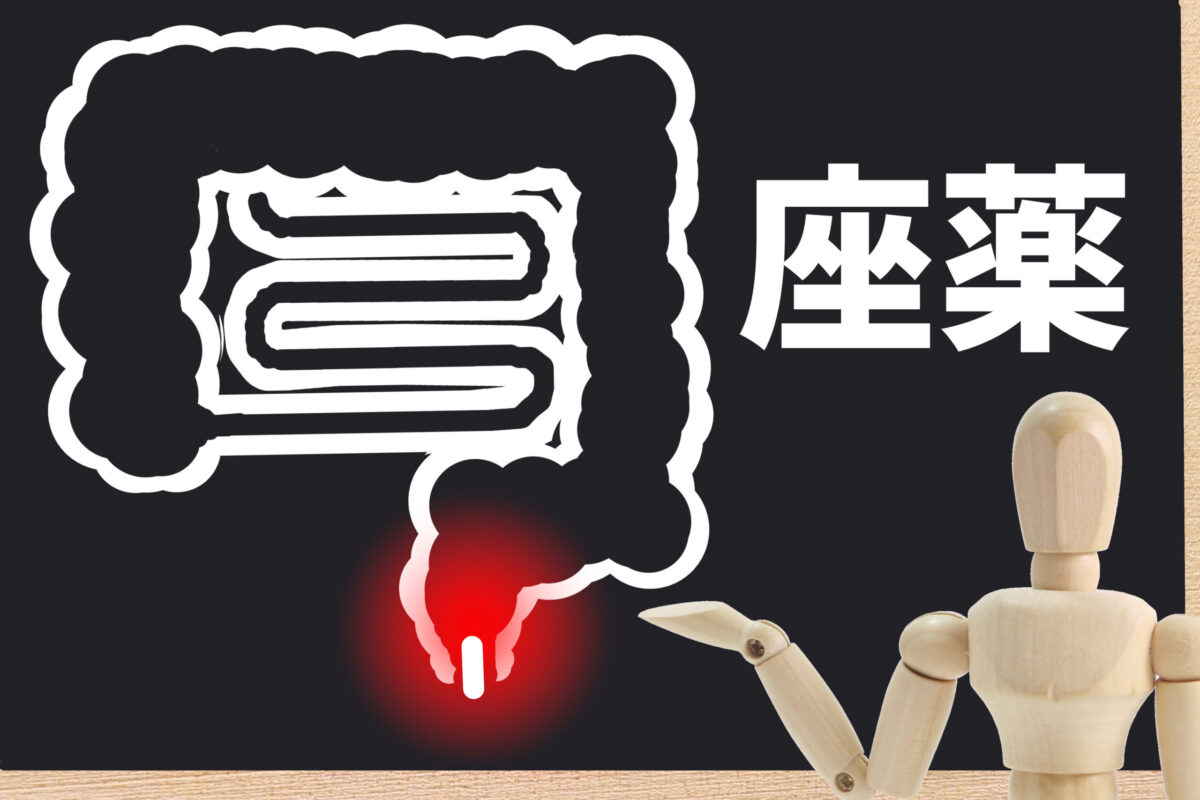
坐薬とは?
坐薬とは、肛門から入れて使う薬のことです。細長く先がとがった形をしています。
痔の薬のように局所的な効果を期待して使うものもあれば、解熱剤のように全身への効果を期待するものなど種類によって目的はさまざまです。
ところで、坐薬と聞いて「座って飲む薬かな?」と思った方はいませんか?
実は、「坐薬(座薬)」という漢字を見て、座って飲む薬だと勘違いされている方がまれにいるのです。
「座薬はちゃんと座って飲んだよ」と患者さんから言われて驚いた経験をもつ薬剤師は意外と少なくありません。
坐薬は肛門から入れる薬ですので、間違っても飲まないようにしてください。
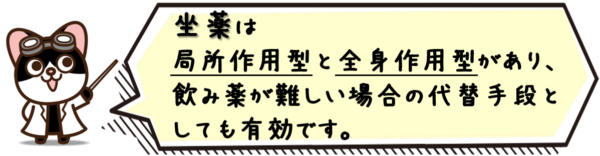
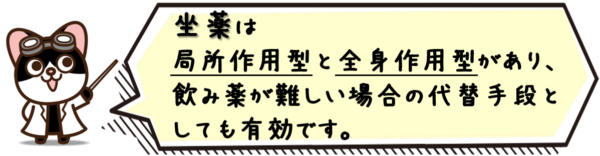
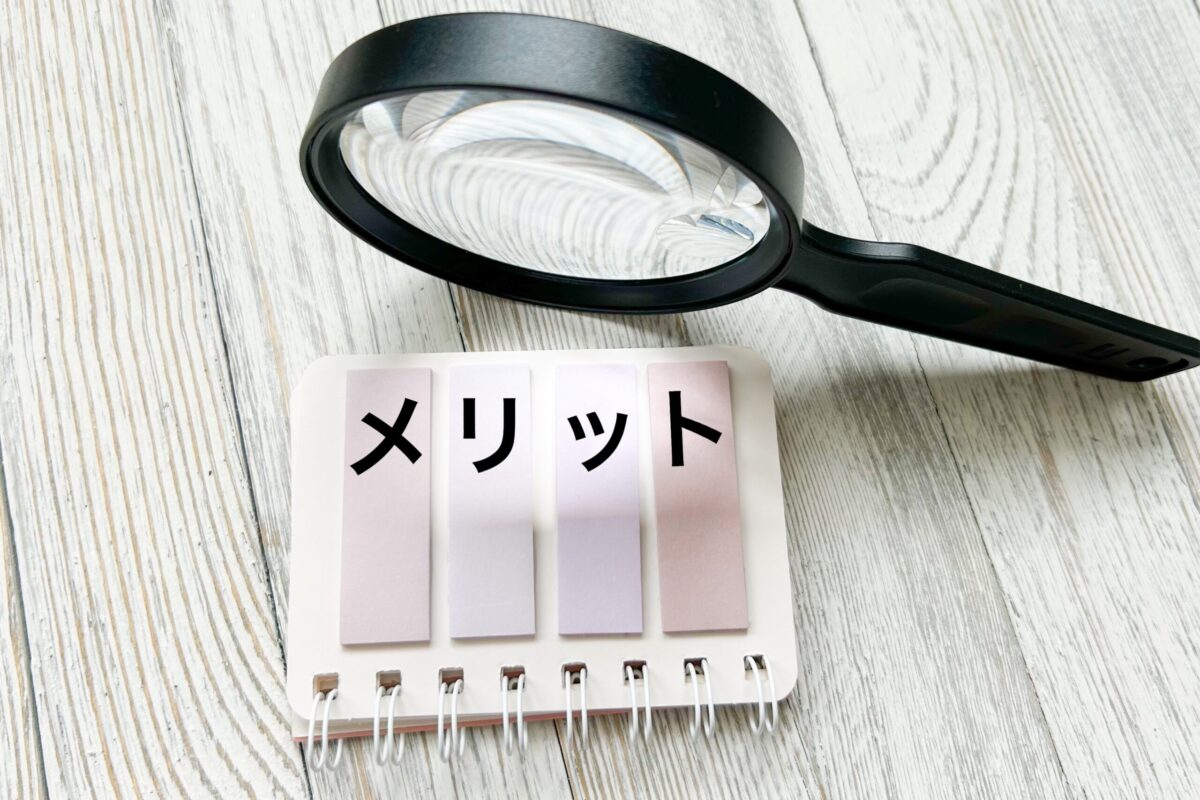
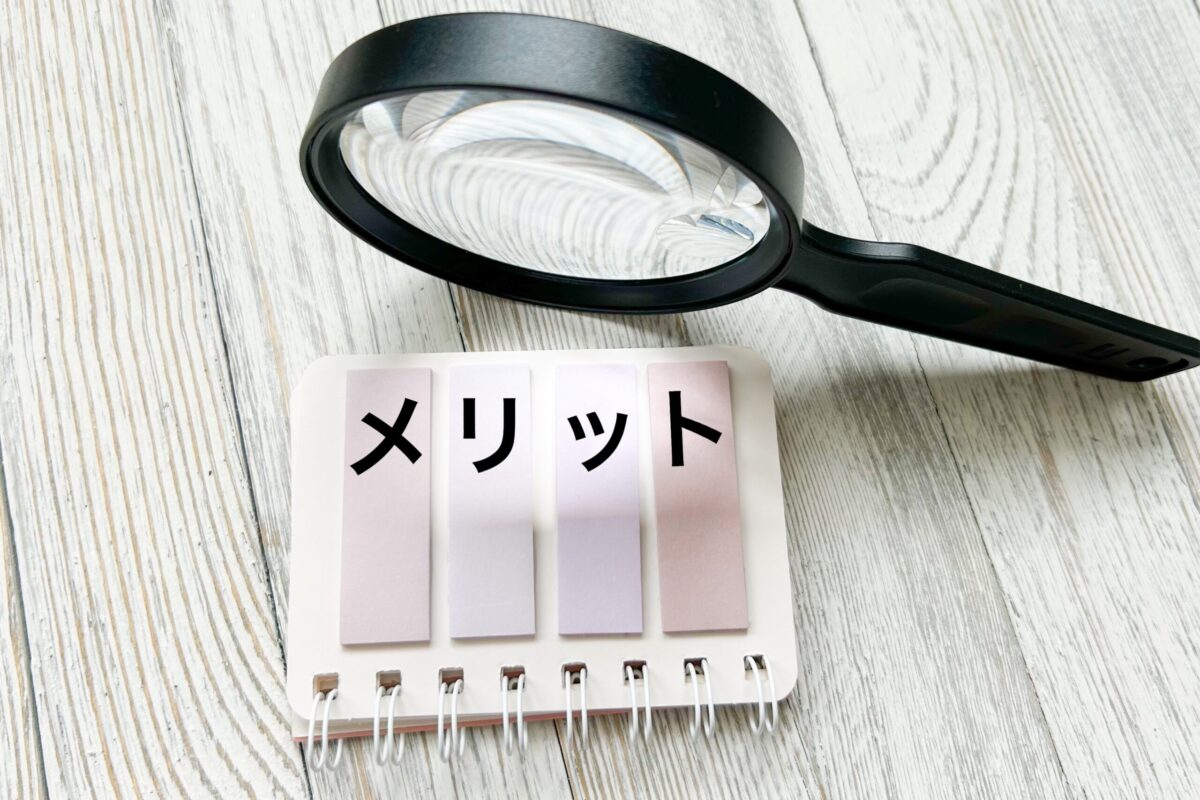
坐薬を使うメリット
坐薬の成分によっては、飲み薬と同じものが使われているものもあります。
それなら飲み薬を使った方が早いのではと思われるかもしれません。
しかし、飲み薬にはないメリットが坐薬にはあります。
飲み薬に比べて吸収スピードが早い
坐薬は飲み薬と比べて早く吸収されやすいことが特徴です。
口から飲んだ薬は胃を通って腸に到達し、肝臓で代謝された後に血液中に入って体へと巡っていき、ようやく効果を発揮します。
坐薬の場合は直腸から吸収され肝臓での代謝を受けずに血液中に入っていくため、飲み薬よりも吸収が早いのです。
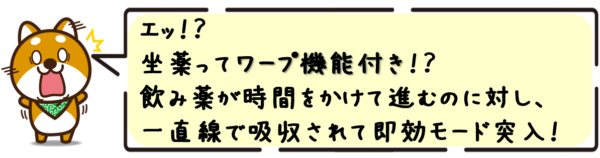
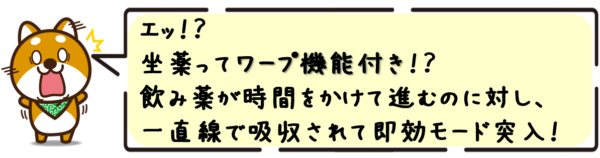
吐き気や嘔吐で口から薬が飲めないときでも使える
吐き気があったり、嘔吐が続いていたりする場合は水すら飲むのが難しい場合があるでしょう。
そのような場合でも坐薬なら肛門から入れるだけなので、問題なく使用できます。
痙攣を起こしていて経口摂取が難しい場合にも有効です。
まだ薬をうまく飲み込めない小さな子どもにもしっかり投与できます。
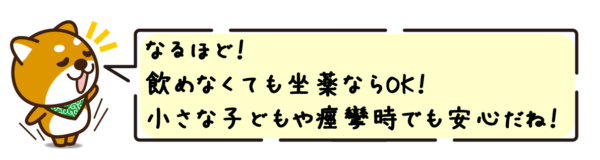
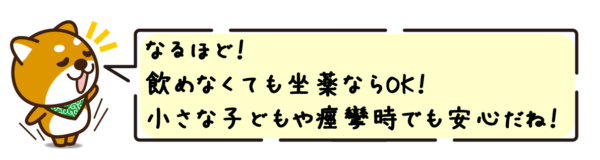
食事のタイミングに関係なく使える
坐薬は食事の影響を受けません。
食前や食後などに配慮することなく、症状が気になるときにいつでも使用できます。
また、薬の成分による胃腸への負担も軽減することが可能です。
解熱鎮痛剤の飲み薬は胃に負担をかけやすいので食後に飲みましょうといわれることが多いですが、坐薬なら胃への負担はほとんどないためいつでも使用できます。
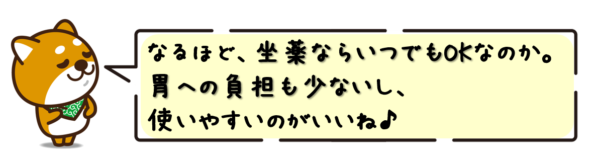
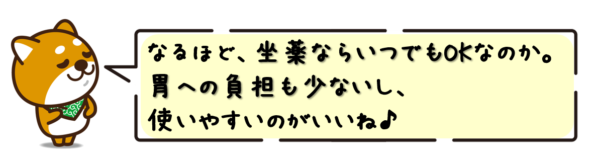


市販の坐薬の種類について
市販では、おもに次の3種類の坐薬が扱われています。
• 解熱鎮痛剤
• 下剤
• 痔疾用剤
解熱鎮痛剤は、熱を下げたり痛みを取ったりするものです。
15歳未満の方を対象とした子ども用の坐剤が販売されています。市販の場合は解熱のみを目的としており、大人用のものは現在のところ販売されていません。
下剤は、便秘の症状を改善する薬です。
直腸を刺激することで排便を促します。
痔疾用剤は、痔の痛みや腫れを抑えるための薬です。
解熱鎮痛剤のように全身には成分が回らず、局所的に効果を発揮することで気になる症状を改善します。
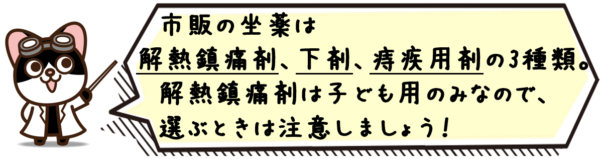
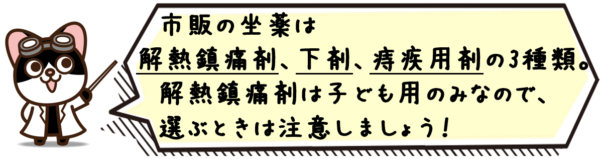
医療用と同じ坐薬は市販で購入可能?
医療用の成分と同じものが使われた坐薬は、市販でも購入できます。
いくつか商品がありますが、ここでは代表的な3つの市販薬について見ていきましょう。
こどもパブロン坐薬
こどもパブロン坐薬は、アセトアミノフェンが主成分の解熱鎮痛剤です。1個あたり100mgのアセトアミノフェンが含まれています。
医療用のアンヒバ坐薬小児用100mgとまったく同じ成分を含む市販薬です。
アンヒバ坐薬小児用100mgは解熱と鎮痛の両方に使用できますが、こどもパブロン坐薬は発熱時の一時的な解熱のみにしか使用できないので注意しましょう。
1歳から12歳の子どもまで使用できます。
オイレスA
オイレスAは、便秘を解消するための坐薬です。
主成分として腸を刺激する効果のあるビサコジルが1個あたり10mg配合されています。
医療用のテレミンソフト坐剤10mgと同じ成分です。
新レシカルボン坐剤S
新レシカルボン坐剤Sは、炭酸ガスによって直腸を刺激し排便を促す薬です。
1個あたり炭酸水素ナトリウムが0.5gと無水リン酸二水素ナトリウム0.68gが配合されています。
医療用では新レシカルボン坐剤というものがあり、成分の種類と配合量は市販薬とまったく同じです。
【番外編】プリザエース坐剤T
医療用とまったく同じ成分というわけではありませんが、成分の一部に医療用と同じものが使われている痔疾用の坐薬があります。
プリザエース坐剤Tは、炎症を抑えるヒドロコルチゾンのほか、痛み止めのリドカインや殺菌成分のクロルヘキシジンなどが配合された市販薬です。
ヒドロコルチゾンなどをはじめ複数の成分が配合された医療用の痔疾用剤として、プロクトセディル坐薬があります。
すべての成分がまったく同じというわけではありませんが、似たような効果が期待できるでしょう。


坐薬を使うときの注意点
坐薬は食事の影響を気にせず使え、小さな子どもでも使いやすいなどメリットがあるものの、注意点もあるので押さえておきましょう。
• 解熱鎮痛剤の使用は一時的なものにとどめておく
• 下剤が配合された坐薬は連用しない
• 市販薬で効果の改善が見られない場合は医療機関を受診する
子ども用の解熱剤として販売されている坐薬は、あくまでも応急処置的に使うものです。
とくに2歳未満の子どもの場合は症状が急変したり早急な対応が必要な疾患が隠れていたりするケースもあるため、医療機関の受診を優先してください。
また、坐薬であっても下剤の成分が含まれるものは連用することで慣れが生じ、効きづらくなってきます。
漫然と使用を続けるのは控えましょう。
また、市販の坐薬を使っても十分な効果が見られない場合は、そもそも市販薬では対処が難しい場合もあります。
効果がないのに使い続けると適切な治療が遅れることがありますので、医療機関を早めに受診するようにしてください。
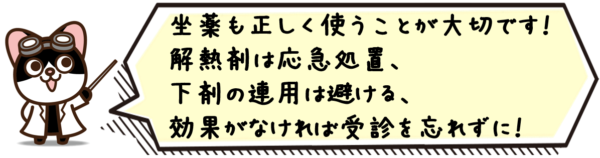
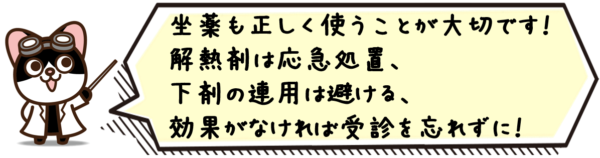
まとめ
坐薬は飲み薬よりも効き目が早く、口から飲むのが難しい場合でも使いやすいことがメリットです。
とくに小さな子どもは錠剤や粉薬を飲み込むのが得意でないことも多いので、坐薬はとても使いやすいでしょう。
市販薬にはアンヒバ坐薬小児用100mgと同じこどもパブロン坐薬、テレミンソフト坐剤10mgと同じオイレスA、新レシカルボン坐剤と同じ新レシカルボン坐剤Sなどがあります。
一時的に処方薬を切らしてしまったときや、市販で購入できる坐薬を探しているときはぜひ参考にしてみてください。